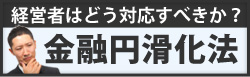従業員の解雇の注意点
解雇には、しっかりしたプロセスがある
会社が破産する場合は、従業員を解雇することになります。
また、会社を破産させずに継続していく場合であっても、やむを得ずリストラの一環として従業員を解雇することもあるでしょう。
解雇が行われると、その有効性を巡って会社と従業員とで紛争になる例が非常に多いですから、解雇の実施に際してはきちんとした法的プロセスを経るだけでなく、従業員の感情的な面にも配慮する必要があります。
なお、一口に解雇とは言っても、解雇の後に事業を継続するつもりなのか、それとも事業を廃止するつもりなのかによって、取るべき手続は異なります。
いずれにせよ、「業績が悪いから」という理由で簡単に解雇できるわけではない、ということはしっかり覚えておいてください。
リストラ等をして従業員の雇用をある程度維持したい場合
一部の従業員について整理解雇を行い、他の従業員の雇用を維持したい場合、過去の判例にて以下の4要件が示されています。
整理解雇はこの要件にすべて適合しないと無効(不当解雇)とされる可能性があります。
1.人員整理の必要性
整理解雇を行うには、人員削減をしなければ経営を維持できないという程度の必要性が認められなければなりません。
2.解雇回避努力義務の履行
解雇は最終手段であることが要求されるため、役員報酬や給与の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、出向等により、整理解雇を回避するための経営努力がなされ、解雇に着手することがやむを得ないと判断される必要があります。
3.被解雇者選定の合理性
解雇するための人選基準が合理的で、具体的人選も合理的かつ公平でなければなりません。
4.手続の妥当性
整理解雇については、手続の妥当性が非常に重視されています。
例えば、説明・協議、納得を得るための手順を踏まない整理解雇は、他の要件を満たしても無効とされるケースが多いです。
また、従業員を常時10人以上雇用している事業所は、法律上就業規則の作成と労働基準監督署への届出義務があるため、整理解雇についての規定や手順を就業規則に盛り込んでいる必要があります。
近く破産予定で、従業員全員を解雇する場合
事業廃止により全従業員を解雇する場合には、整理解雇の4要件とは別の基準で考えることになります。
具体的には、下記の5項目を考慮して手続が妥当であったといえない場合には、解雇権の濫用として無効とされる場合があります。
- 使用者がその事業を廃止することが合理的でやむを得ない措置であったか
(単なる経営戦略上の事業廃止は、使用者が倒産あるいは倒産の危機にある場合に比べて解雇の必要性が低いと判断されます。) - 労働組合又は労働者に対して解雇の必要性・合理性について納得を得るための説明等を行う努力を果たしたか
- 解雇に当たって労働者に再就職等の準備を行うだけの時間的余裕を与えたか
- 予想される労働者の収入減に対し経済的な手当を行うなどその生活維持に対して配慮する措置をとったか
- 他社への就職を希望する労働者に対しその就職活動を援助する措置をとったか
他にもある、解雇をするときの注意点
上記で説明した「整理解雇の4要件」や「事業廃止による全員解雇の要件」を満たした場合でも、簡単に従業員を解雇できるわけではありません。
以下の2つの点にも注意する必要があります。
1.解雇予告期間を30日以上設けること
従業員が当然解雇を言い渡されて路頭に迷わないよう、労働基準法では、従業員を解雇をするときには30日以上の予告期間を設けることが要求されています。
30日以上の解雇の予告期間を設けられない場合は、30日に満たない日数分の平均賃金(過去3ヶ月の給与の日割に相当する額)の支払が義務付けられています。
つまり、前もってしっかりと解雇の準備をしていないと、余計なお金(解雇予告手当)を支払うことになります。
したがって、やむを得ず従業員を解雇しなければならない場合は、余裕を持った計画と予告期間が必要になります。
2.解雇ができない人がいる
下記に該当する従業員は、その事由に該当している間または該当しなくなった日後30日間はどのような理由でも解雇することができません。
- 業務上の傷病による休業期間
- 産前産後の休業期間
また、下記のような理由で従業員を解雇することはできません。
整理解雇において下記を基準にして人選を行った場合、解雇が無効になります。
- 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
- 会社の不正等を労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
- 労働組合の組合員であること等を理由とする解雇
- 女性(男性)であること、女性の婚姻、妊娠、出産、産前産後休業等を理由とする解雇
- 育児・介護休業の申出をしたこと、育児・介護休業を取得したことを理由とする解雇
- 通常の労働者と労働条件がほとんど変わらないパートタイム労働者を、パートタイム労働者であることを理由とする解雇
- 公益通報(事業所の不正等を通報)をした者に対し公益通報した事を理由とする解雇
弁護士や社会保険労務士にご相談ください!
このように会社を整理する上で従業員を解雇する場合には、法律や過去の判例等による厳格なルールが適用されます。
繰り返しにはなりますが、「業績不振だから」という理由で会社が簡単に従業員を解雇することはできません。
廃業や事業再生のために従業員を解雇しなければならない場合には、トラブル防止のため、事前に弁護士や社会保険労務士等の専門家に相談されることをお勧めします。
High Fieldグループでは、弁護士と社会保険労務士が協力してアドバイスをさせていただきます。
無料相談受付中!まずはお気軽にお電話下さい。
- 会社の倒産とは
- 会社の倒産手続の種類
- 早めのご相談を!
- 会社・法人の自己破産
- 会社・法人の破産手続の流れ
- 会社破産のメリット
- 会社破産のデメリット
- 会社破産の注意点
- 管財事件・破産管財人
- 債権の種類と優先順位
- 債権者からの督促への対応
- 会社財産の処分はちょっと待った!
- 滞納税金はどうなる?
- 連帯保証人への影響は?
- 会社破産後の従業員の生活
- 従業員への給料の支払は
- 従業員の解雇
- 従業員解雇・退職後の諸手続
- 雇用保険(失業保険)等の手続
- 会社破産後の社長の生活
- 自宅はどうなる?
- 社長・経営者個人の債務整理
- 自己破産(社長個人)
- 個人再生
- 任意整理(社長個人)
- タイプ別診断
- 民事再生
- 会社更生
- 任意整理
- 調停・ADR
- 中小企業再生支援協議会
- 特別清算
- 解散・清算
- 再チャレンジを応援します!